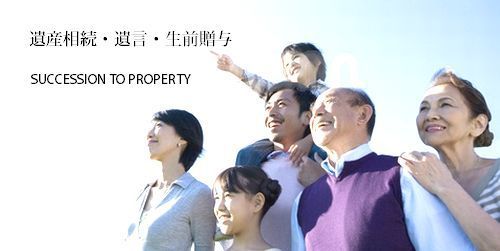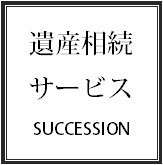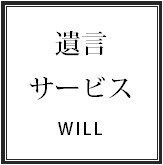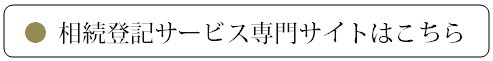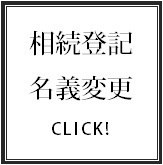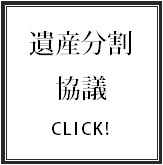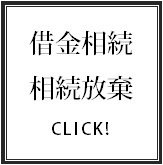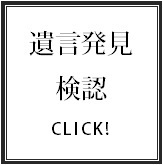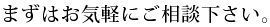愛知・名古屋の登記や法律相談に強い司法書士なら初回は無料相談できる名古屋市中区の司法書士事務所まで☝
登記や法律の無料相談なら栄駅・矢場町駅すぐの名古屋登記サロン☝
【 平日 】 | 午前 9:00 〜 午後 8:00 |
|---|
【 土日 】 | 午前 9:00 〜 午後6:00 ( 完全ご予約制☝) |
|---|
☝遺産相続の無料相談が名古屋で出来る名古屋市中区の相続相談窓口。
各種相続手続き・相続登記・生前贈与・遺言等のご相談なら愛知県名古屋市中区の遺産相続無料相談窓口☝
『 真心 』こめてお手伝い。
Service Line
名古屋都心で遺産相続に習熟し厳選されてきた専門家が、お客様のご予算に合わせて、必要なサービスを必要なだけご提供いたします。
☝どんな『遺産相続』も1つの窓口で解決
●当事務所では、「遺産相続」に関連するさまざまな事例への対応が可能です。「遺産相続に関する各種手続き」のご相談のみにとどまらず「 法定相続人間で紛争性を帯びているようなケース」 「 相続税対策が関連するケース 」 「 相続放棄等のため緊急性を要するようなケース」など、必要に応じて各種提携専門家とともに迅速・正確に対応いたします。
●当事務所は、これまで培ってきた経験とノウハウ、そして人的資産を生かして、お客様が必要とされるサービスを必要なだけご活用いただけるよう、充実したサービスラインをリーズナブルな料金体系でご用意させていただいております。
●複雑な案件・紛争性の高い案件・税金対策などが必要な場合は、提携の弁護士・税理士・社会保険労務士・財務コンサルタント等の専門家とともにワンストップサービスを実現いたしますので「あんしん」です。
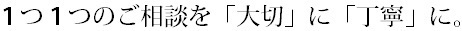
●シンプルな案件から複雑な案件に至るまで、まずは当事務所の相続アドバイザー・専門相談員が何なりとご質問にお答えいたします。
●まずはお気軽に無料相談サポート

☝ 遺産相続 の 総合相談窓口です。
Service Line
専門家ネットワークにおよるワンストップサポートにより、お客様のご予算に合わせて、必要なサービスを必要なだけご利用いただけます。


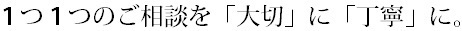
☝ 遺言についてのトータルサポート
●「 遺言 」はそもそも何と読むのが正式なのでしょう?「 ゆいごん? 」「 いごん? 」職業柄、法律の専門家は「 いごん 」と読み、一般の方は「 ゆいごん 」と読まれる方が比較的多いと思われますが、どちらの読み方も正解ということでしょう。
●遺言を作成される目的はそれぞれおありだと思いますが、その一般的な目的の1つは、「相続トラブルを未然に防止するため 」の手段として作成がなされることが多いといえます。ただし、一定の形式を備えた遺言でなければ、その効力は認められず、また、その内容が不十分な場合には、相続人間の争いの火種にもなりかねませんので、遺言作成には十分な検討と注意が必要といえます。
●当事務所では遺言に関する充実したサポートを提供させていただいております。遺言に関する知識・理解不足が引き起こす、いろいろな諸問題に注意しなければなりません。
●遺言とは、遺言作成者の最終意思を尊重し、その記載がなされている内容に従い、遺産の振り分け等が行われるわけですが、遺言を作成する際や、若しくは遺言を発見された場合など、その遺言の取り扱いには細心の注意が必要となります。
●また、故人の部屋から遺言が発見された場合の対処方法や、遺言により相続分を排除された相続人からの遺留分減殺請求についてのご相談など、当事務所にはさまざまなお客様がご相談におみえになられます。
●遺言のことでお困りの際は、当事務所の相続アドバイザー・専門相談員までまずは何なりとご相談下さい。
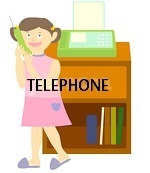
☝ ご相談の一例
● 遺言を作成したのだけれど、保管方法を教えて
● 相続人間で争いが起こらない遺言をつくりたい
【 遺言の専門サイトへ 】
● 遺言執行者について知りたい。 遺言信託とは?
【 家族信託の専門サイトへ 】
● 遺言を発見した!遺言を預かってる!どうする?
● 遺言を作成しが気が変わった!変更できる?
● 愛犬のために財産を残したい!犬への遺言は?

☝ 遺言サービス一覧
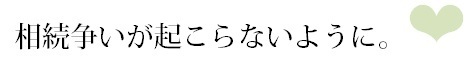
Service Line
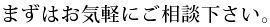

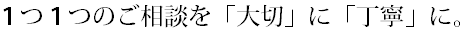
☝ 生前贈与・譲渡についてサポート。
●生前贈与・その他譲渡(交換・売買等)を上手に活用することにより、次世代へのスムーズな財産承継を実現することが可能となります。
●生前贈与を行う理由はたくさんございます。① 相続までほおっておいては、多額の相続税がかかるケース ② 長男・跡取りへのより確実な不動産の引き継ぎのため ③ 逆に跡取り以外の子供への財産分割のため ④ 各推定相続人の公平をきすため などなど
●なお、どの理由であるにせよ、生前贈与において最も注意しなければならないのが、税金面での問題です。
●年間110万円の無税贈与枠の活用・相続時精算課税のメリットとデメリットなどの税制を如何に活用して「最もお得となる生前贈与プランを実現していくのか」が大切となります。
●慎重な税務プランニングを要する場面も多く、専門家との連携を図らずになされた贈与については、相応のリスクが伴うものです。
●生前贈与時に必要各種手続きから税金対策に至るまで、当事務所の相続アドバイザー・専門相談員が提携税理士とともにお客様にとって最適な生前贈与プランをご提案差し上げます。
●お気軽に電話無料相談サポート
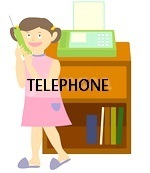
☝ ご相談の一例
【生前贈与専門サイトへ】
【生前贈与専門サイトへ】
【税理士のサイトへ】
【生前贈与専門サイトへ】
【生前贈与専門サイトへ】
【税理士のサイトへ】

☝ サービス一覧
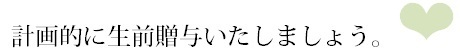
Service Line
☝ 安心・信頼 の 相続手続きサポート。
すべての相続が1つの窓口で解決できる遺産相続の総合相談窓口で、必要なサービスを必要なだけ☝相続手続きは『 いろいろ☝』

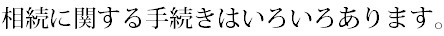
☝ 遺産相続時の各種手続き
遺産相続が発生した場合に、まずは何をしていけばよいのでしょうか。必要となる手続きは、お客様ごとの相続状況によりある程度異なることとなりますが、まずは一般的といえる共通の相続手続きについて以下のようなものがあげられます。
● 死亡届
被相続人がお亡くなりになられてから、原則7日以内に被相続人の最後の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に。医師の死亡診断書とともに死亡届を提出する必要があります。
● 死体火葬(埋葬)許可申請
被相続人がお亡くなりになられてから、原則7日以内に、上記死亡届の後、市区町村役場に申請します。
● 世帯主変更届
相続発生から、原則14日以内に、住所地の市区町村役場に届け出ることになります。
● 児童扶養手当認定請求書(必要に応じて)
相続発生から、原則14日以内に、上記世帯主変更届とともに住所地の市区町村役場に届け出ることになります。
● 婚姻関係終了届(必要に応じて)
相続発生後住所地又は本籍地の市区町村役場に届け出ることになります。
準確定申告
遺産相続発生後4ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告することが必要です。詳細は担当税理士にご相談下さい。当事務所提携税理士による税務相談もご活用いただけます。
相続税の申告
原則、相続税が発生する場合、各種税務特例措置を活用する場合には、相続発生後10月以内に、管轄税務署に申告することが必要です。提携税理士によるご相談、サポートをご活用下さい。
在職中のケース(勤務先に対する手続き)
死亡退職届、退職金・給与の受領、保険証の提出等、相続開始後速やかに勤務先への手続きをいたしましょう。
☝ 調査確認が必要な事項
● 遺言書があるかどうかの確認→自宅等に自筆証書遺言が残されているかどうか、公正証書遺言が作成されているかどうかの確認
● 相続人の調査→法定相続人を調査確定する必要があります。
● 相続財産の調査→金融資産、株券・私募債等の証券資産、不動産資産等、相続の対象となる財産を全て洗い出すことが必要です。
●法定相続人及び相続財産が明確になったら、通常、相続人全員による遺産分割協議を行い、相続財産の振り分けを行います。
●被相続人が不動産を所有していた場合、相続による不動産(土地・建物・マンション等)の名義変更登記が必要になります。また、被相続人様を債務者とする担保権が設定されている場合の担保権に関する登記(抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記・根抵当権変更登記等)が必要になります。
☝ 裁判所関係
● 自筆証書遺言が発見された場合のその開封には注意が必要です。まずは開封せずに裁判所に提出するとともに遺言検認手続きをしなければなりません。また、遺言があることを隠し隠匿することは違法となりますので気をつけましょう。
● 遺言がある場合、相続人は遺言の内容に従った財産の振り分け等(遺言の執行)を行うことになります。遺言執行者を選任する必要がある場合は、その選任を行った上で、遺言執行者が遺言の執行を行うことになります。
● 被相続人に多額の借金がある場合や、借金がある可能性が高い場合は、相続放棄申述申立て又は限定承認申立てをすることになります。相続財産を勝手に処分する等の行為をしてしまった場合は、法定単純承認とみなされ、相続放棄手続きや限定承認手続きが出来なくなりますので注意が必要です。
●法定相続人間において遺産分割協議が整わない場合は、遺産分割調停→遺産分割審判により裁判所をとおして取り決めていくことになります。多大なお金と時間、労力が必要となるため、出来れば協議分割(法定相続人全員の話し合いでとりまとめ)で解決したいものですね。
●遺言の内容に「全ての財産をAに相続させる」等の記載のある場合でも、法定相続人には、法律で守られている相続分(遺留分といいます)を有しています。しかしその権利は遺留分損害額請求という形で行使しなければその効力を生じません。
☝ その他
● 埋葬費、葬祭料等の公的支給、各種年金に関すること、未支給失業給付金等につきましては、社会保険労務士にご相談いただけます。
● 生命保険金、入院保険金、団体弔慰金、簡易保険、医療費控除の還付請求、死亡退職金、遺族共済年金、埋葬料、生命保険付住宅ローン、クレジットカード等、もらえるものはしっかり確認の上、もらっておきましょう。
● 各種保険、公共料金、NHK、銀行口座、預貯金講座、賃貸不動産、各種証券(株券、債権等)電話、特許権、著作権、貸付金、出資金、各種免許・届出、自動車、自動車納税義務者、ゴルフ会員権等、名義変更はお忘れなく。
● 各種カード、携帯電話、借金、各種会員証・メンバーズカード、運転免許証、リース・レンタルサービス等の解約手続きをお忘れなく。
お問合せ・ご相談

お名前・ご用件をお聞かせ下さい。
担当者へお繋ぎさせていただきます
☎ どんな些細なことでもお気軽に☝対応時間外は【24時間】留守電☎又は✉対応で安心☝(052)269-4010
【平日】9:00~20:00【土日】9:00~18:00(要予約)
サービスメニュー
登記や遺産相続もお気軽に☝
対応時間外も【24時間】受付中
司法書士
HATTORI LEGAL OFFICE
司法書士 服部雄一郎 ☝
住 所
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目15番33号
栄ガスビル4階
アクセス
●栄駅6番16番出口より徒歩3分
●矢場町駅6番出口より徒歩1分
●松坂屋北館より0分
※北館1・5階渡り廊下よりガスビルへ直通◎
受付時間
【 平日 】9:00 ~ 20:00
【 土日 】9:00 ~ 18:00
(完全予約制)
業務エリア
〓 名古屋全域対応 〓
名古屋市の中区・東区・西区・北区・熱田区・中村区・千種区・中川区は近くて便利です。また名古屋市の南区・港区の港湾エリアから緑区・瑞穂区・昭和区・天白区・名東区・守山区に至る内陸部エリアまで名古屋全16区に迅速対応☝
〓 愛知県全域対応 〓
春日井市・尾張旭市・長久手市・瀬戸市・小牧市・北名古屋市・日進市やあま市・清須市・稲沢市・一宮市・津島市エリアからも沢山ご相談いただいています。
〓 知多半島・三河 〓
大府市・東海市・豊明市から半島沿いに知多市・半田市や代表司法書士の出身地である岡崎市・刈谷市・碧南市・高浜市・西尾市・知立市への対応も喜んで。